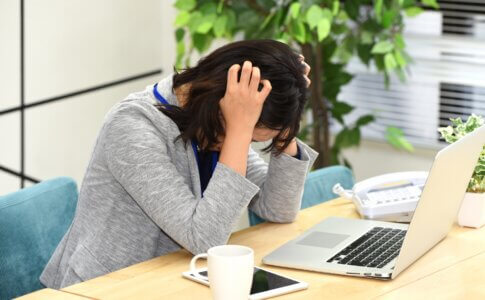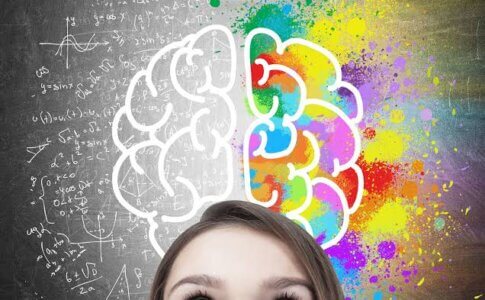目 次 【 押すと ジャンプ します 】
『甘やかし』を考える
先日、ウチの娘(小6)が、髪型を変えたので、
「かわいいよ」「似合ってるよ〜」を連発していたら、
「父ちゃんの評価とか
いらないから」
と、バッサリ斬られたのでした。
結構、ツンデレで雑に扱われてるんで、たまにイラッともくるのですが、そんな仕打ちを受けても、それでもベッタリしてしまう、、
各方面から
「甘やかしすぎだって!」「ひいきしすぎ」と言われます。
ですが、あえて言います。
「私は娘を ひいき します。」
というか、
その「役割」を担います。

「甘えさせない」は伝染する
余談になりますが、

こんな親御さんも多いのですが、これは実は非常に危険な状態で
正直、「自分がしたくてもできなかったこと」を他者に容認するというのは、人間精神的に相当難しいのです。
顕在意識(建前)では、「自由に甘えさせる」と言いながら
心の奥、潜在意識の深い部分では、甘えている我が子をみると、
どうしても嫉妬にも似た憎しみが湧いています。
「私は必死に耐えてきたのに」「許せない」という感情が湧きます。
これを抑えている状態です。
感情の抑圧、強引な正当化、心理的逆転という状態で、
体に重篤な症状として現れます。
本人も氣づかないです。
この状態のお母さんは、旦那さんや爺ちゃん婆ちゃんが子供を甘やかしているのを見ると、
イキリ立って怒ります。奥底で、
「自分はできなかったのに
簡単にそれをするとは何事だ」
という強い反発がうまれているのですが、
「我が家の躾によくない」などと正当化して阻止しようとします。
「本人の好きな職業につかせます」
なども、親御さん自身にそのトラウマがあると口で言ってるのと感情が真逆になり非常に苦しむことになります。子供側もその周波数に気づくため親を立ててフリをします。
お互いがとても苦しくなります。
このケースでも、対処法はやはり「キヅク」ことにつきます。
- 『私、子供が甘えてるのをみると「イラっと」きてるなぁ』
▶︎感情認識 - 『自分もあんなふうに甘えさせてほしかったんだなー』
▶︎自分に寄り添い
これで強い反発心は成仏します。

これを読んで「もや」っときた方、お心当たりのある方はご利用ください。
長らく存在した「甘えは良くない」時代
強い人間になってほしい・忍耐力をつけてほしい…
厳格な躾として「甘やかし」はダメなこと。
こんな風潮が長らくありました。
一見、ちゃんとした人間が育ちそうですが
この風潮は
「自己受容感 」の欠如
を生み出しました。
親の評価によって、
甘えることが”できたり””できなかったり”したため
「できない自分」は認められない。
「甘えることができた経験」が少ないと、
自分が自分を認めるという事の意味がわからず、
自分のココロを無視して他者評価を基準にして行動するため
ココロは魂レベルで
ザクザク傷ついていきます。
他者からみると、ぱっと見、
氣づかいができて、謙虚な素晴らしい人間と評価されますが
その実、本人のココロは悲鳴をあげている
というのが昭和世代に非常に多いのでした。
無自覚でそうなっています。
自分をココロを抑えた傷は、 年齢が上がるに従って、 人生の早い段階で、どんどん「地雷撤去」することが肝要です。 
決して消える事なく
「地雷」のように体にセットされていきます。
この鬱積したストレスが連続爆発し
ガンや心疾患、脳卒中といった
「溜め込み・破裂系」の病気へと発展するのです。
近年では、甘えは決して「良くないもの」ではなく、
愛情の発達に不可欠な要素
として、昨今では「甘やかし」専門で研究されている偉い人たちも、たくさん存在します。
なぜなら「自己受容感」「自立への基盤」として非常に重要な発達段階だと理解されつつあるからです。
甘えとは
「他者の好意や保護を当然のように期待し、依存し、かつそれが受け入れられることを前提とした感情」である。
(土居, 1971)
甘えは、乳幼児期に唯一の対象「母親」へ依存する形として現れます。

甘えの肯定は自立の前提

「抱っこされたい」「見ていてほしい」「一緒にいてほしい」乳幼児〜期間は、ひたすら求めてきますよね。
これらの欲求が抵抗なく受け入れられ、自然に満たされる。
このように甘えられた子は
「あるがままで受け入れられる経験」
を通じて
「絶対の安心感」
「いつでも愛されている感」
を、身につけます。
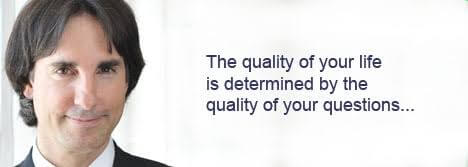
この人は子供時代は発達障害児のレッテルを貼られていて「将来、まともな大人にはなれない」と教師に言わしめた子でしたが、両親だけはそれを信じていなかったようです。
ディマティーニ青年が旅に出ると言い出した時、ハイウェイの道端で彼をおろして別れ際に
「あなたが何になろうが、何をして過ごそうが、
これだけは知っていてほしいの。
あなたのお父さんとお母さんは、
いつでも、いつまでも、ずっとあなたを愛しているわ。」
この言葉がディマティーニのチャレンジ精神を安心した形で促したことになったのでした。
この言葉には
「例え、息子が、
犯罪者になろうがホームレスになろうが、
それでも愛してる」
という意思も含んでいることを確信できたのでした。
この
「いつでも愛されている感」は
子供自身のココロというボールを
柔らかいベールで包んでくれます。
これは一生モノです。
こうなると、世間は「恐ろしいもの」「怖いところ」ではなくなります。
自分で考え自分で行動する余裕が生まれます。
つまり、本当の自立ができます。
プラス「自分が受け入れられている」と感じると、
人のことも受け入れる余裕ができます。
周囲は「敵」ではなく「仲間」として見られるため、
一般的にいう
「おおらかさ」がナチュラルに身につきます。

逆に、甘えを許されなかった場合・・・
甘えが満たされない、あるいは否定された子どもは、
なんとか甘えさてほしい、興味を持ってほしいと
周囲の期待や評価に自分を合わせようとします。
いわゆる「他人軸」というやつです。
大人になってからのストレスのほとんどが
他人軸である事に起因します。
自分のしたいこと、思ったこと、言いたいことをグッと飲み込み「いい子」を演じます。自分のココロより、他人の評価・愛情がほしくて無理します。(無意識に)
こうやって不安を回避する傾向があります。
上記のメタファーでいうと、
ココロを守ってくれるベールが無く、
丸裸で不安な状態です。心細いですよね(´Д`)」
自身でキヅかないと、
この行動基準で生き続けます。
筋反射テストをすると一発でわかります。 とても辛い人生になります。 もはや自分の人生じゃなくなってますからね。 
これにまつわるトラウマ・観念がウン百個も埋め込まれています。
自分の本心を、いつでも後回しにするので、
自分で考えることができない、
または
自分の考えを否定されるのが怖い
という意識状態になり
情緒の柔軟性、創造力、自己表現などが
低レベルとなります。
子供でいうと、
- 一人遊びができない
- 動画ばかりみている(アルゴリズムで自動的に出てくる動画を漫然とみる)
- 遊びかたがわからない。
などなど…よく耳にする話しです。
上記の理由が大きいようですね。
逃げ場としての「甘えられる存在」
とはいえ、「甘えさせる」って線引きが難しいですよね。
親側の基準によります。千差万別。
私的な考えでいうと、
成長につれて
いろんな、しがらみ、制限が出てくる中で、
一点でもいいので
存分に「甘えられる」 人 、 場所 が
あればいいのかと思います。
母親や先生は厳しくても、父親や婆ちゃん爺ちゃんは無条件に甘やかす。みたいな。
ところを、
どっかで発散する。
それでバランスがとれればプラマイゼロでオッケーです。
周囲の人間も役割があるってことですね。
それでバランスをとっていければ、平坦に甘やかされるよりも、
人間関係・人間心理の成長に大きな学びになるはずです。

学校でも縛り付けられ、
家族全員がビシビシと厳しくて、
逃げ場がない状態…
この「甘えられる」存在が全くいなかった場合
- 他者を警戒し、
- 自分の存在すらも信用しない
「観念」が出来上がってしまいます。
自分を信用できないので、あらゆる恩恵・幸せを受け取らなくなり、
それでも自己価値を上げたいので
弱い立場の人を見つけて、マウントを取るなどの行為で
バランスを取ろうとします。
前にも書きましたが、
イジメをする子は
どこかでイジメられています。
見た目は優秀ですが、自己受容感が低いため幸福度が非常に低くなります。
カラダも不健康として現れます。
ただの「甘やかし」…
だけど、そういった
バランスをとる役割があることを
知って愛情持って「甘やかす」と子供のココロは強く柔らかくなっていくと思います。
「甘える」ことの必要性を世間的・親側が受け入れる。
「育ちに不可欠なもの」として積極的に甘えさせる場面も必要ということを腑に落としましょう。
実際の対応としては 無条件の応答性:子どもの訴えにすぐ応じること。評価せず、まず「いること」で応える。 身体的なふれあい:抱っこ・おんぶ・膝の上など、皮膚感覚を通じた安心の経験。 予測可能な関係:急な変化や気分で対応しない、日々同じように関わる「わかってくれている」感の蓄積。 参考:『「甘えと遊び」をめぐる発達的・神経生理学的考察』 より
こうした関係性のなかではじめて、
「安心」して
「チャレンジ」し
「世の中・人生は面白い」と思える土台ができるようです。
🆁🅴🅲🅾🅼🅼🅴🅽🅳🅴🅳 ▶︎▶︎

Example…